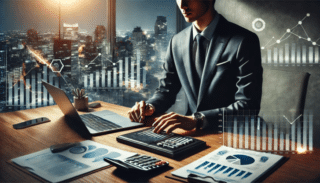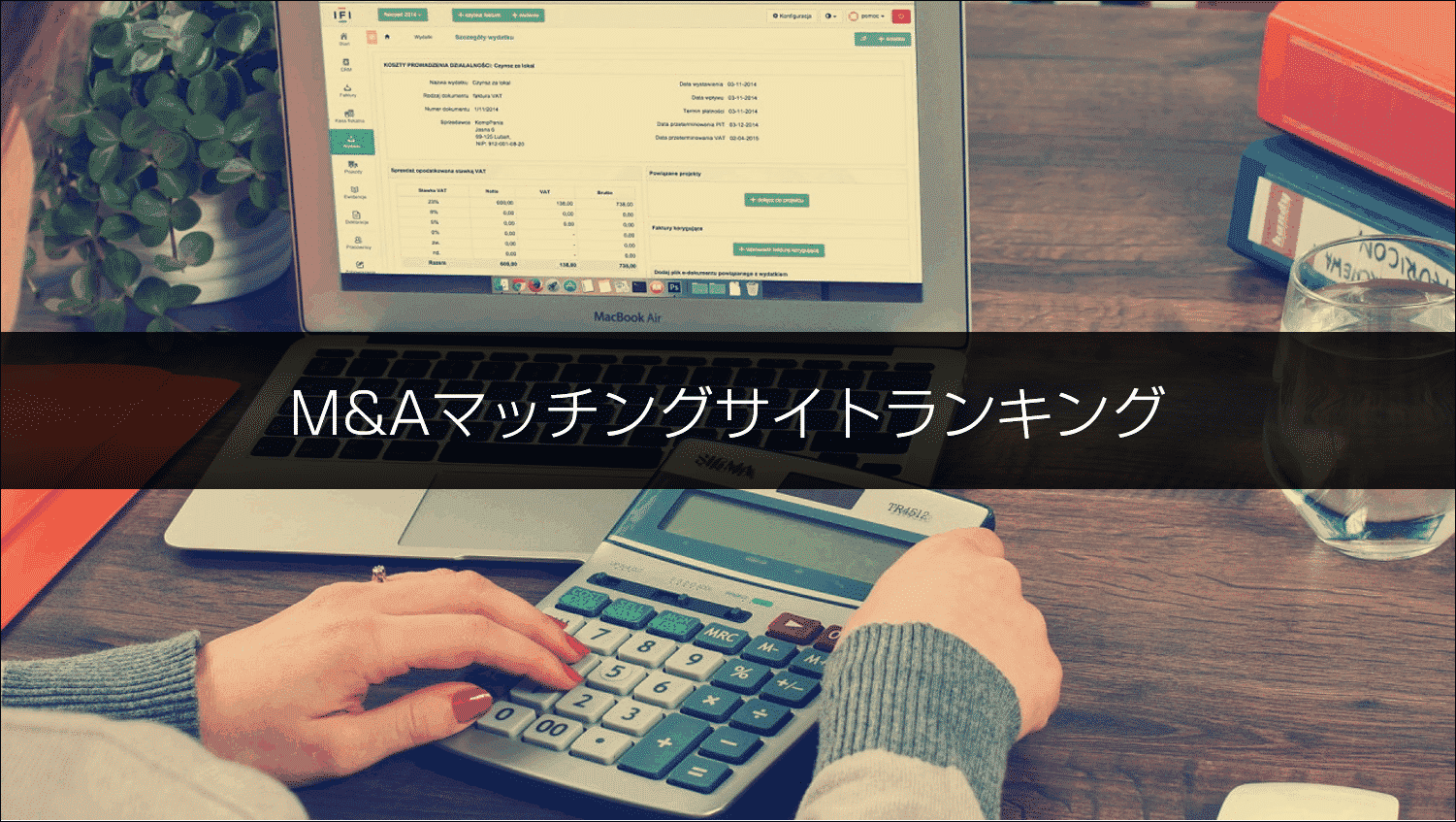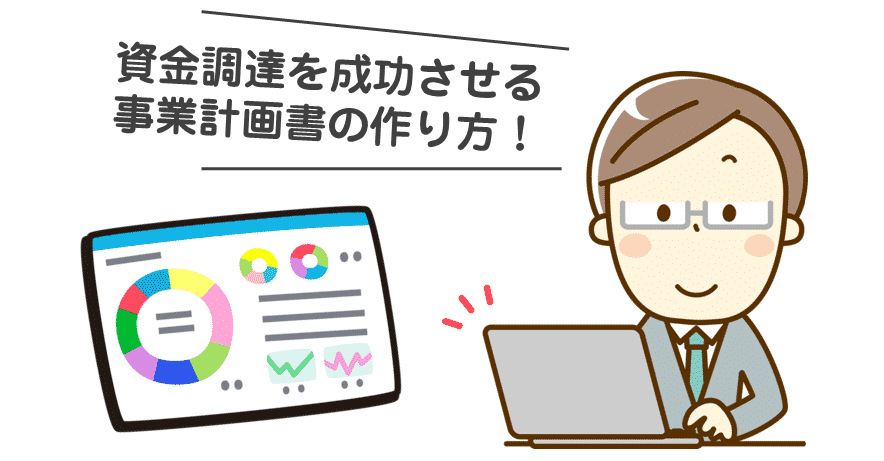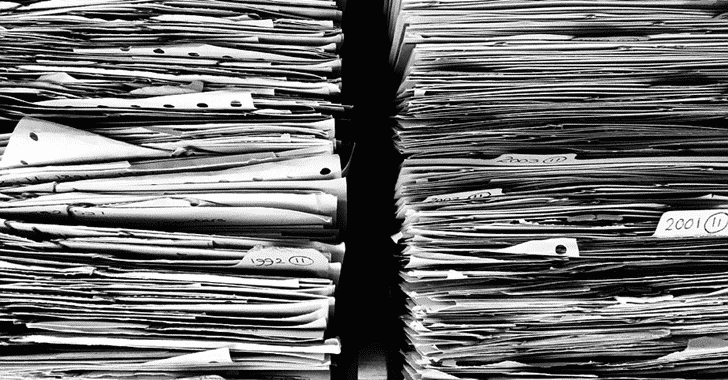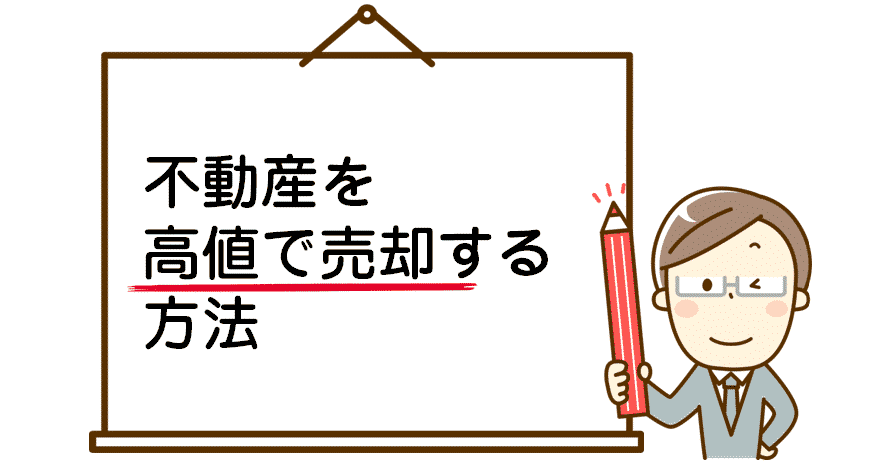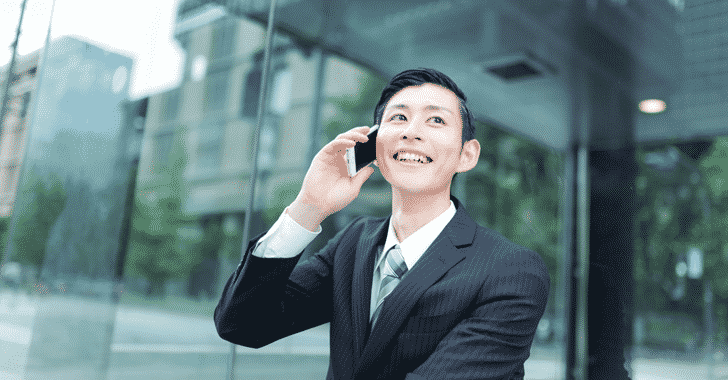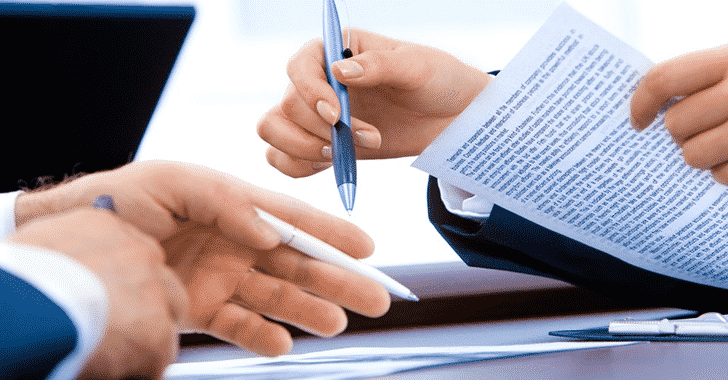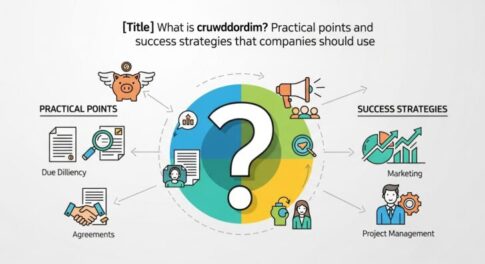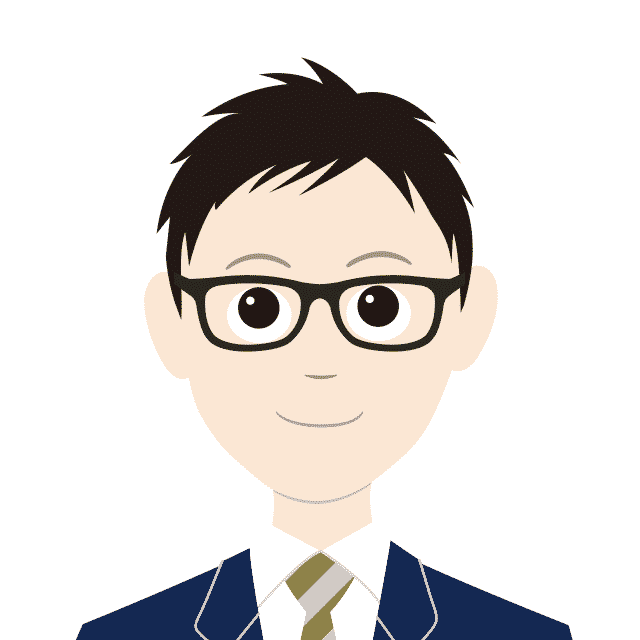ICOとは?企業の資金調達に使える理由
ICO(イニシャル・コイン・オファリング)は、企業が独自のトークンを発行し、暗号資産(仮想通貨)と引き換えに資金を調達する手法です。従来の株式発行や金融機関からの借入とは異なり、ブロックチェーン技術を活用して、インターネット上で不特定多数の投資家から直接資金を集めることができます。
この仕組みの特徴は、資金の受け皿が「企業」ではなく「プロジェクト単位」である点にあります。企業の信用力や担保の有無よりも、プロジェクトの将来性やユニークさが投資判断の軸となるため、特に革新的な事業アイデアを持つスタートアップと親和性が高いとされています。
ICOにはいくつかの形態があります。一般的なICOのほか、信頼性を高めるために暗号資産取引所が審査を行う「IEO(Initial Exchange Offering)」、さらに分散型取引所を利用した「IDO(Initial DEX Offering)」も登場しており、技術の進化とともに選択肢が広がっています。
発行されるトークンにも種類があります。代表的なのが以下の2つです。
- ユーティリティ・トークン:プロジェクトが提供するサービスへのアクセス権など、将来の利用価値に紐づけられたトークン。ゲーム、メディア、コミュニティ系のサービスと相性が良い傾向があります。
- セキュリティ・トークン:株式や債券など金融商品と同様に、出資に対する配当や資産価値が伴うトークン。法的には証券とみなされ、金融商品取引法の対象になります。
こうしたICOは、グローバルに開かれた市場で迅速な資金調達を可能とする一方、法制度や税務面での整備が追いついていない点が課題となっています。そのため、制度対応を見据えた戦略的な設計が求められます。
ICOによる資金調達のメリット・デメリット
【メリット】信用力に依存しない資金調達が可能
ICOの最大の利点は、企業の財務状況や過去の実績といった「信用力」に依存せず、プロジェクト単位で資金を調達できる点にあります。特に、革新的な技術やサービスを構想しているが、まだ十分な売上や資産がないスタートアップにとっては、有望な選択肢となり得ます。
また、国内外を問わずインターネット経由で資金提供者を募ることができるため、資金調達の範囲がグローバルに広がる点も大きな魅力です。実際、短期間で数十億円規模の資金を集めたプロジェクトもあり、伝統的な調達手段では到達困難なスピードと規模を実現できます。
さらに、ユーティリティ・トークンのようにプロジェクト利用権などの「機能」を付与することで、単なる投資ではなく、サービスへの関与や参加を促すことができる点も、マーケティングやコミュニティ形成において有効です。
【デメリット】制度面での不確実性と高い運用ハードル
一方で、ICOには解決すべき課題も多く存在します。最も大きな障壁は、制度整備の遅れです。日本では、資金決済法や金融商品取引法による規制が厳格で、IEOやSTOを除く自由なトークン販売は事実上困難です。
また、税務面では、調達時に受け取った暗号資産が一時的に課税対象となり、資金繰りに大きな影響を及ぼすケースもあります。会計処理においても基準が明確でないため、監査対応や財務報告上のリスクが発生しやすくなります。
加えて、発行するトークンの設計やホワイトペーパーの作成、技術的なスマートコントラクトの実装、さらには外部の法律・会計専門家との連携など、プロジェクト遂行にあたって求められる体制は高度で複雑です。
ICOは柔軟性と革新性に富んだ資金調達手段ですが、実行するには相応の準備と専門的な知見が不可欠です。制度対応やリスク管理を前提としたプロジェクト設計が求められます。
実例から学ぶICO資金調達|日本企業の最新事例
日本においては法制度上の制約がある中でも、工夫を凝らしてICOを活用する企業が出始めています。ここでは、国内で実際に行われたIEOの先進事例である「Palette Token」のケースをもとに、法人がトークン発行を通じてどのように資金を調達したのか、その背景と効果を解説します。
Palette Token|日本初のIEOによる資金調達
2021年、ブロックチェーン関連のスタートアップ企業である株式会社HashPaletteは、日本で初となるIEO(Initial Exchange Offering)として「Palette Token(PLT)」を発行しました。発行企業は、上場企業Link-Uとブロックチェーン企業HashPortの共同出資により設立された法人で、IEOは暗号資産取引所コインチェックとの連携で実施されました。
このプロジェクトの主目的は、NFT(非代替性トークン)の発行・流通・管理を行うブロックチェーンプラットフォーム「Palette」の開発資金を確保することにありました。トークンの購入者には、NFTの発行権や将来的なサービスへの優先アクセス、プロジェクト方針の投票権などが付与される設計がなされており、ガバナンストークンとしての性質を持っていました。
資金調達のスキームと結果
Palette Tokenは、発行総数10億枚のうち、IEOを通じて2.3億枚を市場に放出。価格は1トークンあたり4.05円で設定され、調達金額はおよそ9.3億円にのぼりました。IEO実施時点での応募者数は6万人を超え、国内では異例の注目を集める結果となりました。
上場後はトークン価格が急騰し、90円を超える場面もあり、投資家にとってもリターンの大きな案件となりました。一方、発行企業側は開発費に充てる潤沢な資金を確保すると同時に、トークンエコノミーを通じて長期的な事業成長の基盤を構築しました。
トークン保有と会計・税務への対応
このケースでは、発行後も2.7億枚のトークンを企業が保有する形となっており、ガバナンストークンとしてプロジェクト統治の安定性を担保する役割を果たしています。
加えて、令和5年度の税制改正により、自社発行のガバナンストークンが期末時点で時価評価の対象外とされる方向性が示されたことから、企業会計上のリスクも大幅に軽減されつつあります。このような制度整備の進展が、今後の日本国内でのICO推進を後押しすると見られます。
企業がICOを選んだ理由
HashPaletteがIEOという形でトークン発行を選んだ背景には、次のような戦略的な判断があります。
- NFT市場という成長分野において、従来の資金調達では時間や信用面のハードルが高かった
- コミュニティ形成やプロジェクト参加型のトークンエコノミーを構築したかった
- 法制度上のリスクを最小限に抑えるため、取引所を介したIEO形式を採用した
このように、IEOの活用は単なる資金調達手段にとどまらず、プロジェクトへの共感者を巻き込むマーケティング戦略としても機能しています。
法人にとっての示唆
Palette Tokenの事例は、日本国内においても適切な法的スキームを組むことで、ICO型資金調達が十分に現実的な選択肢であることを示しています。とくに、ガバナンストークンを含むユーティリティトークンの活用は、スタートアップ企業やWeb3系プロジェクトを展開する法人にとって、資金調達と事業推進を両立する手段となり得ます。
制度対応を踏まえた計画的な準備と、IEOなどの信頼性あるスキーム選定が鍵となります。専門家の協力を得ながら、資金調達と事業価値創造の両立を目指すことが、ICO成功の条件といえるでしょう。
ICO実施時の会計・税務リスクと対応策
【会計】現状の会計基準と未整備なポイント
ICOで発行されるトークンに関する会計処理は、現時点では明確な基準が存在しません。企業会計基準委員会の「実務対応報告第38号」では、他者発行の暗号資産については一定の取扱いが示されているものの、自社発行トークンについては対象外とされています。
特に問題となるのが、発行時の資金受領をどのように処理するかです。資本金として計上できない場合、収益計上や負債認識の判断が求められ、会計処理にばらつきが生じる可能性があります。さらに、発行後も企業が保有し続けるトークン(ガバナンストークンなど)について、期末における評価方法も整理が必要です。
2022年以降、会計基準策定に向けた議論は進んでいるものの、いまだ統一的な指針は定まっておらず、監査対応や財務開示における不確実性が残ります。財務諸表に対する説明責任を果たすうえで、個別のトークン設計に応じた慎重な会計判断と、監査法人との事前協議が不可欠です。
【税務】発行時の一括課税リスクとその緩和策
ICOによりトークンを発行し、対価として暗号資産を受け取った場合、その受領額は収益として一時に課税対象となります。特に、トークンに明確な義務や対価提供が伴わない設計であれば、資金受領の全額が即時に課税対象となる可能性があります。
この一括課税は、プロジェクトが未着手の段階でも法人税が発生することを意味し、資金繰りに大きな影響を与えるリスク要因です。調達額の30%以上を税として支出せざるを得ないケースも想定され、ICO計画の資金設計には十分な留意が求められます。
一方で、会計処理において収益認識基準を適用し、資金受領時に負債計上を行うことで、税務上も収益の繰り延べが認められる可能性があります(法人税法22条の2等)。ただし、これはプロジェクト遂行の確実性や契約上の履行義務が求められるため、ホワイトペーパーにおける記載や実務遂行体制の整備が前提となります。
税務署の判断により、会計と税務の処理が一致しないリスクもあるため、事前に税務当局や専門家と連携し、処理方針を固めておくことが望まれます。
【令和5年改正】ガバナンストークンの時価評価除外とは?
これまで、自社発行トークンを期末時点で保有している場合、たとえ市場に流通していなくとも、市場価格による時価評価が求められていました。この仕組みは、現金収入のない含み益に課税が発生するという点で、スタートアップ企業などにとって大きな負担となっていました。
令和5年度税制改正により、一定の条件下における自社発行トークン、特にガバナンストークンについては時価評価の対象外とされる措置が講じられました。これにより、プロジェクト継続のために手元に残すトークンが課税対象から外れ、財務的な安定性が確保されやすくなります。
ただし、この改正は自動的にすべてのトークンに適用されるわけではなく、対象となるトークンの種類や保有目的について明確に説明できる体制が必要です。ホワイトペーパー上での用途明記や、社内ガバナンスに関する文書整備もあわせて行うことで、税務リスクの軽減につながります。
法人がICOを活用する場合、会計・税務の各種リスクに加え、制度未整備によるグレーゾーンが多く存在します。これらのリスクを踏まえたうえで、初期段階から税理士や会計士、監査法人などの専門家と協議を重ねることが、健全な資金調達の鍵となります。
資金決済法など法規制の影響と対処法
ICOによる資金調達を日本国内で実施する際には、資金決済法を中心とした厳格な法規制が大きな障壁となります。とくに、暗号資産を「業」として取り扱う場合は、暗号資産交換業者として内閣総理大臣の登録が必要であり、未登録の一般企業が投資家に直接トークンを販売することは原則として認められていません。
このため、法人がICOを行う場合には、登録済の暗号資産交換業者を介したIEO(Initial Exchange Offering)という形式を選択するのが現実的です。IEOでは、取引所がトークン発行の審査や販売を代行するため、コンプライアンス面での信頼性が高く、投資家保護の観点でも評価されています。ただし、新規上場の審査には一定の時間とコストを要し、柔軟なスケジュールでの資金調達には限界がある点も留意が必要です。
一方、近年では分散型取引所(DEX)を用いたIDO(Initial DEX Offering)も登場しています。IDOでは、スマートコントラクトによって自動的にトークン販売が成立するため、暗号資産交換業者が存在せず、従来の規制が必ずしも適用されない可能性があります。ただし、日本国内の投資家を対象とした場合には、資金決済法の域外適用が問題となり、実質的に日本市場向けのIDOも規制対象とみなされる可能性があります。
さらに、海外に法人を設立し、日本人投資家向けにICOを行うケースも見られますが、この場合でも「実質的に日本国内で提供されるサービス」と判断されれば、資金決済法の規制を受けることになります。たとえば、ホワイトペーパーが日本語で記載されていたり、販売サイトに日本国内向けの広告表示がされている場合などは、日本の居住者をターゲットとした提供とみなされるリスクがあります。結果として、海外法人であっても、日本の暗号資産交換業者としての登録が必要になる可能性があるため、慎重な運用設計が求められます。
このような状況下で、日本におけるICOを検討する法人にとっては、IEO形式による実施、または国内向けトークン販売を控えてグローバル市場を中心とした展開に切り替えるなど、現行法に即したスキームの構築が不可欠です。特にIEOについては、すでに国内でも複数の事例があり、法規制に対応したスキームのモデルケースとして活用できます。
また、規制環境の変化にも柔軟に対応する必要があります。今後、Web3関連産業の成長を促進するために、暗号資産の取り扱いに関する法制度が見直される可能性もあり、最新のガイドラインや金融庁の動向を継続的にフォローすることが重要です。
法規制の影響を最小限に抑えるためには、弁護士や暗号資産に精通した専門家との連携は不可欠です。ICO計画の初期段階から、リスク管理と法的適格性を担保した設計を行うことで、後々の是正指導や行政対応の負担を軽減できます。規制環境を正しく理解し、それに沿った資金調達スキームを構築することが、法人にとっての成功への第一歩となります。
法人がICOで資金調達する際のステップと注意点
ICOによる資金調達は、法務・税務・技術の各分野にわたる高度な設計と調整を必要とするプロセスです。法人が自社でICOを実施する際には、単にトークンを発行すればよいというわけではなく、事前の検討から発行後の運用管理に至るまで、段階ごとに注意すべきポイントが存在します。
検討段階で確認すべき5つのポイント
- トークン設計の目的と機能
ユーティリティトークンとしての設計か、セキュリティトークンに該当するのかによって、適用される規制や開示義務が大きく異なります。資金調達後に提供すべきサービスや権利内容を明確化し、金融商品取引法や資金決済法との整合性を確認する必要があります。 - 法的スキームの構築
国内でのICOは規制が厳しく、現実的にはIEOを通じた実施が中心となります。必要に応じて、海外法人設立やグローバル市場向けの発行も選択肢に含め、適法性を担保したスキーム構築が求められます。 - ホワイトペーパーの策定
トークンの価値やプロジェクトの目的、資金の使途、発行数量、ロックアップ条件などを明確に記載したホワイトペーパーは、投資家保護の観点からも極めて重要です。虚偽記載や誤解を招く表現は将来的な訴訟リスクに繋がるため、リーガルチェックが不可欠です。 - 資金使途と収益化戦略の整合性
調達した資金がどのようにプロジェクトに還元されるのか、その見通しが曖昧であれば、収益認識基準の適用や税務上の繰延処理も難しくなります。資金調達と事業遂行の一貫性を担保する戦略設計が必要です。 - 市場選定とトークン流通戦略
上場を予定している暗号資産取引所の審査基準や取扱方針に合わせて、販売価格・ステーキング制度・流通制限などの条件を検討します。適切なマーケティングと流通計画がトークンの価値維持に直結します。
必要書類と関係機関との調整事項
ICOを実施するためには、以下のような書類整備と外部機関との連携が必要となります。
- ホワイトペーパー(日本語/英語)
- 利用規約・プライバシーポリシー
- 資金決済法関連の届出書類(IEOの場合)
- 内部統制文書・資金流用防止体制の説明書
- 金融庁・日本暗号資産取引業協会(JVCEA)との調整資料
IEO形式を採用する場合、提携する取引所側での審査や事前届出が義務付けられており、複数回にわたる書類提出とフィードバック対応が求められます。スケジュールには十分な余裕を持たせることが重要です。
外部専門家と連携すべき領域
ICOの実行にあたっては、社内リソースのみでは対応が困難な領域が多く存在するため、専門家との協働が不可欠です。
- 弁護士(金融法務・知財・海外法対応)
規制の適用可否やホワイトペーパーのリーガルチェック、訴訟リスク管理に関与。 - 税理士・会計士(ICO専門対応実績のある者)
収益認識、期末評価、税務申告、監査対応における方針策定。 - スマートコントラクト開発者/監査会社
トークン発行・販売プロセスに用いるスマートコントラクトの設計・検証。 - 暗号資産取引所とのリエゾン担当者
IEO申請から上場後の運営までの調整業務。
各専門家と早期に連携し、情報の非対称性を最小化することが、ICO成功の鍵を握ります。とくにガバナンストークンの設計や収益認識方法の妥当性判断は、事業全体の信頼性に直結する重要ポイントです。
ICOは法人にとって革新的な資金調達手段となり得ますが、その分、制度的・技術的なリスクも複雑化しています。万全な準備と専門的支援の下で、段階的にプロセスを踏むことが不可欠です。
まとめICOは有望だが、慎重な戦略設計が必要
ICOは、法人が従来の手法にとらわれず、プロジェクト単位でグローバルな資金調達を実現できる強力なツールです。とくに、資産や信用力に乏しいスタートアップ企業にとって、ユーティリティトークンやガバナンストークンの活用により、将来の成長価値を担保とした資金流入を可能にする点は大きな魅力といえます。
一方で、現在の日本国内においては、会計・税務・金融規制の整備が未成熟な領域も多く、慎重な計画と体制構築が求められます。令和5年度の税制改正など、制度的な前進も見られるものの、依然としてグレーゾーンが多く残っており、プロジェクトの設計次第で企業が背負うリスクは大きく異なります。
法人がICOを成功に導くためには、以下の3つの視点からの戦略設計が不可欠です。
- 制度への適合性の徹底確認
トークン設計・発行スキームが金融商品取引法や資金決済法に抵触しないかを精査し、必要に応じてIEO等の形式を選択することで、法的リスクを回避します。 - 会計・税務の影響を見据えた設計
資金調達時の収益認識、期末評価、ホワイトペーパー上の義務明記など、将来的な税負担・監査リスクを最小化するストラクチャーを採用する必要があります。 - グローバル市場との接続性
日本国内だけでなく、海外投資家や取引所も視野に入れたマーケティングやスキーム設計を行うことで、柔軟かつ持続可能な資金調達基盤を構築できます。
ICOは革新的な仕組みである一方、成功には多角的な検討と専門家との密な連携が求められます。法制度や市場環境が目まぐるしく変化する中で、継続的な制度ウォッチと柔軟なアップデート対応が、競争優位性の確保につながります。中長期的な成長と信頼を両立させるためにも、実行可能な範囲での段階的な戦略構築が鍵を握ります。